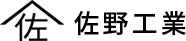焼き方によって異なる「瓦の種類」について
こんにちは!
京都市右京区にある屋根工事会社「佐野工業」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
陽光に輝く穏やかな波。
瓦屋根は、建物を守ってくれる美しい外装材です。
瓦と言えば、もっぱら屋根瓦のことを言いますが
じつは床に敷く「敷き瓦」や、壁に張る「壁瓦」もあります。
敷き瓦寺院で、壁瓦は土蔵などでみることができます。
瓦が日本に入ってきたのは6世紀ごろ。
その頃は、平瓦と丸瓦を合わせた本葺きがメインで
現在使われている桟瓦(さんがわら)は
江戸時代になってからあらわれたものです。
瓦を普及させたのは、その耐久性、断熱性です。
形や色もさまざまにあり、建物のデザインに応じて
幅広いバリエーションから選ぶことができるのも
普及した要因のひとつといえます。
瓦は、製造過程の焼きかたによって
次のように分類されています。
【いぶし瓦】
焼きあがる直前に松葉などをくべて、表面に炭素被膜を作ったもの。
美しい暗灰色をしているところが特徴です。
【塩焼き瓦(赤瓦)】
焼き上がり前に塩を投入して、表面にガラス状の皮膜を作った
赤褐色の瓦です。耐寒性が強いので、寒冷地での使用に適しています。
【釉薬瓦】
酸化鉄、マンガンなどの釉薬をかけて焼き上げたもので
赤・緑・青など、さまざまな色に仕上げられています。
強くて防水性に優れています。
【磨き瓦】
表面を雲母などで磨いて防水性を高めており
渋い光沢がある瓦です。
屋根工事、瓦工事、瓦のずれや雨漏りなど
屋根に関することは「佐野工業」へ!
どうぞお気軽にお問い合わせください。